- 2025-6-25
- 医療保険
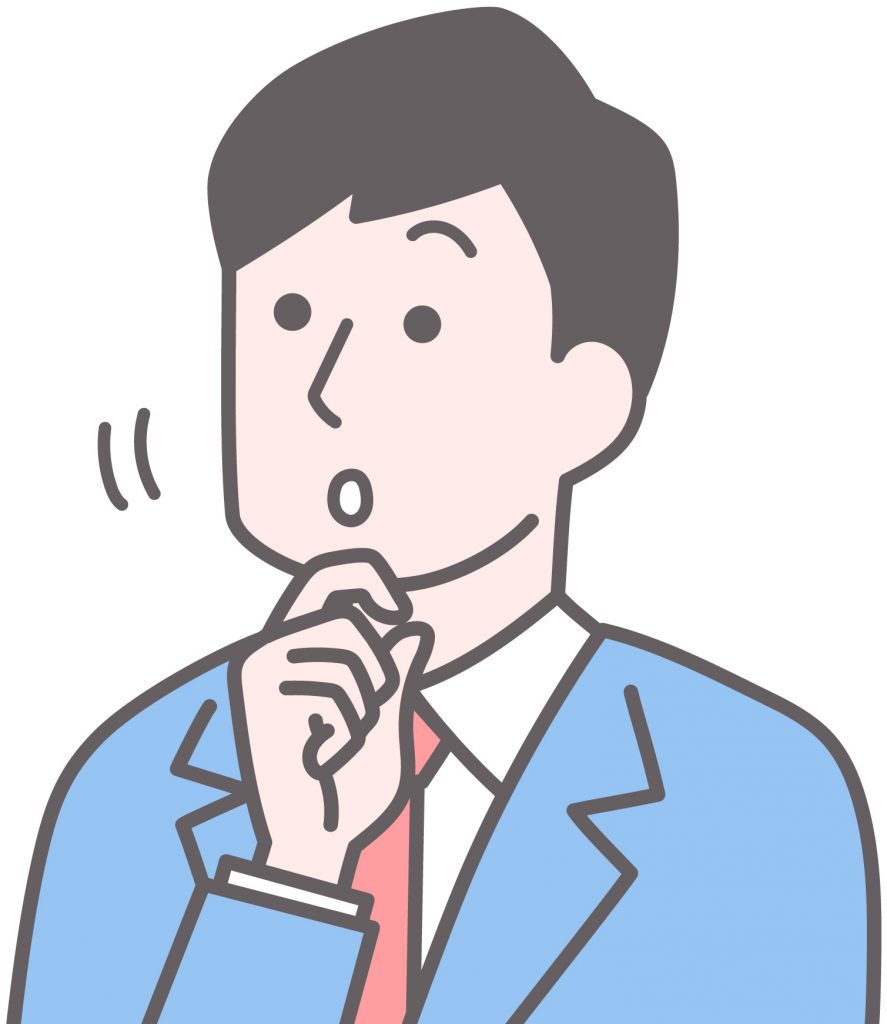
病気やケガの治療後に必要となることが多い「リハビリテーション」。長期にわたることも多く、費用面での不安を感じる方も少なくありません。では、民間の医療保険ではリハビリも補償されるのでしょうか?ここでは、医療保険とリハビリの関係について、制度の概要から注意点までを段階的に解説してまいります。
目次
- リハビリとは?医療行為としての位置づけ
- 医療保険はリハビリも補償するのか?
- 入院・通院リハビリの扱いと保険金給付の条件
- 対象外となるケースとその理由
- まとめ
-
リハビリとは?医療行為としての位置づけ
リハビリテーション(以下、リハビリ)は、病気やケガによって失われた身体機能の回復や、生活能力の向上を目指す医療行為です。脳卒中後の後遺症に対する機能訓練、骨折後の関節可動域訓練、高齢者の歩行訓練など、対象は多岐にわたります。
医師の診断のもと、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの専門職によって行われる医療的な訓練であり、健康保険の対象にもなることから、医療保険でも一定の条件を満たせば補償対象となります。
-
医療保険はリハビリも補償するのか?
医療保険でリハビリが補償されるかどうかは、そのリハビリが「治療の一環」として行われているかどうかがカギです。たとえば、骨折による入院後の関節機能の回復を目的としたリハビリや、脳梗塞後の機能訓練などは、多くの医療保険において給付対象となります。
保険会社が重視するのは、「医師の指示のもとで、医学的に必要と判断されたもの」であるかという点です。したがって、自由診療や健康増進目的のトレーニング的なリハビリは、保険の対象外となる可能性が高いです。
-
入院・通院リハビリの扱いと保険金給付の条件
リハビリが入院中に行われる場合、入院給付金の対象として扱われることがほとんどです。リハビリ期間が長くなったとしても、医師の管理下での入院が続いている限り、契約した日数分の給付金を受け取れるケースが一般的です。
一方、通院リハビリに関してはやや複雑です。医療保険に「通院給付特約」が付いていない場合、通院のみでは給付されない場合もあるため、事前に契約内容を確認することが重要です。
たとえば、「脳卒中で10日入院し、その後3か月間通院してリハビリを受ける」というケースでは、入院期間に対しては給付があるものの、通院リハビリに対しては、特約がなければ給付が出ない可能性もあるということです。
-
対象外となるケースとその理由
以下のようなケースでは、リハビリであっても医療保険の対象外となることがあります。
- 予防的リハビリ:健康増進目的や要介護状態への移行予防など、治療とは直接関係のない場合
- 美容目的のリハビリ:見た目の回復を目的としたもの(例:美容整形後の施術)
- 診断書のない自費リハビリ:医師の指示や診断に基づかない場合
また、接骨院や整体などで行う施術も、医療機関での正式なリハビリとは見なされないことが多く、医療保険の給付対象外となる可能性が高いです。
-
まとめ
リハビリは、病気やケガの回復において非常に重要なステップであり、場合によっては生活の質に直結します。その費用負担を軽減するためにも、医療保険による補償の有無をあらかじめ確認しておくことは極めて重要です。














