- 2025-8-20
- 医療保険
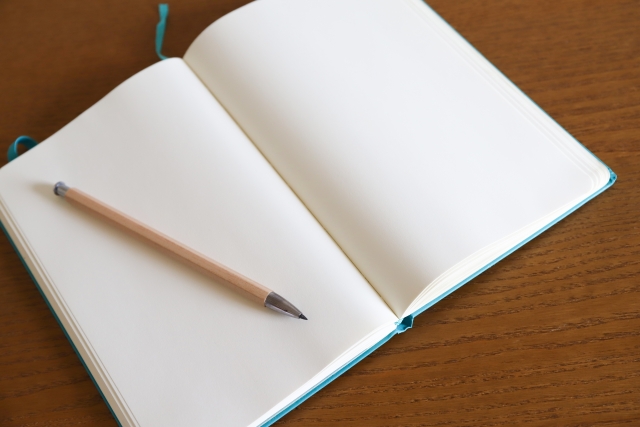
日本の公的医療保険制度は、1922年の健康保険法制定から始まり、1961年に国民皆保険が実現するまで急速な進化を遂げてきました。さらに、後期高齢者制度の導入や自己負担率の変更など、現在までに複数回の見直しが行われています。本記事では、歴史的な流れをふまえつつ、制度の推移をステップ形式で整理し、理解を深めていきます。
目次
- 1922年:健康保険法の制定と被用者保険の始まり
- 1938年:国民健康保険法制定と地域型保険への展開
- 1961年:国民皆保険制度の実現
- 1973年以降:高齢者医療の制度整備と自己負担の見直し
- 2008年以降:後期高齢者医療制度の導入とその改革
-
1922年:健康保険法の制定と被用者保険の始まり
日本の医療保険制度のスタートは、1922年に制定された健康保険法にあります。この制度は主に企業に勤める労働者を対象とした被用者保険として始まり、1927年に施行されました。都市部を中心としたこの制度は、当初は加入対象が限られていたものの、社会保険制度の基盤として重要な役割を果たしました。
-
1938年:国民健康保険法制定と地域型保険への展開
被用者保険だけでは加入対象が限定される問題を受け、1938年には国民健康保険法が制定され、自営業者や農漁村の住民にも保障が拡大されました。しかし、制度の普及は戦争や行政体制の不備により遅れており、1950年代まで未加入者の割合は非常に高い状態が続きました。
-
1961年:国民皆保険制度の実現
1958年の制度改革により市町村単位で国民健康保険の運営が義務化され、その整備が進んだ結果、1961年に「国民皆保険制度」がついに完成しました。これにより、全ての国民がいずれかの公的保険に加入することが義務化され、医療へのアクセスが飛躍的に向上しました。
-
1973年以降:高齢者医療の制度整備と自己負担の見直し
高齢化が進む中、1973年には70歳以上の医療費無料化が始まります。これにより老人医療制度が進展し、多くの高齢者の医療負担が軽減されましたが、財政面の負担が社会問題化したため、1983年には一定の自己負担を求める老人保健法が施行されました。
-
2008年以降:後期高齢者医療制度の導入とその改革
高齢化が一層進行する中、2008年に後期高齢者医療制度が導入され、75歳以上(一定の障害のある65~74歳を含む)を対象とする新たな医療保険制度が確立されました。さらに2015年には医療保険制度改革法が成立し、医療費負担の見直しや制度運営の効率化が図られました。
-
まとめ
日本の医療保険制度は、1922年の健康保険法に始まり、1961年には全国民を対象とする皆保険制度を確立。その後は高齢化に対応した制度改革を重ね、現在に至っています。各時代背景に応じた制度変更が、医療アクセスの拡大や財政の持続可能性確保につながっている点が特徴です。














