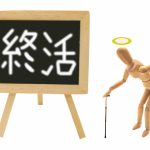- 2025-4-17
- 個人年金・年金

少子高齢化が進む現代において、年金制度は多くの人にとって将来の生活基盤を支える重要な仕組みです。ところが、「将来、本当に年金はもらえるのか」「金額は増えるのか、減るのか」といった不安の声も少なくありません。この記事では、国民年金と厚生年金の過去から現在にかけての受給額の推移を通して、将来設計に役立つヒントを探っていきます。
目次
- 年金制度の基本構造
- 国民年金の推移から読み解く変化
- 厚生年金の受給額の動き
- 推移から考える将来の生活設計
- まとめ:数字の変化が教えてくれること
-
年金制度の基本構造
日本の年金制度は、20歳以上のすべての人が加入する「国民年金」と、会社員や公務員などが対象となる「厚生年金」の二階建て構造となっています。国民年金は基礎年金とも呼ばれ、全ての人に共通して支給されるものです。一方、厚生年金は報酬比例で、加入期間と給与水準に応じて金額が変わります。これらは老後の生活を支える公的年金として位置づけられており、その支給額の動向は多くの人にとって関心の高いテーマです。
-
国民年金の推移から読み解く変化
国民年金は、定額で支給されるため、物価や賃金の変動に大きくは左右されませんが、近年は微細な調整が行われています。たとえば、令和3年度末の平均受給額はおよそ5万6千円でしたが、令和4年度には5万2千円と若干の減少が見られました。その後、令和5年度には5万8千円と持ち直す傾向を見せています。これは、マクロ経済スライドという仕組みによって、物価や賃金に応じて自動的に調整が行われるためです。このように、国民年金は安定性を保ちつつも、経済の変動に応じて柔軟に対応しているのが特徴です。
-
厚生年金の受給額の動き
厚生年金は、加入者の報酬と加入期間によって大きく異なりますが、全体の平均値を見ることで制度の傾向を把握することができます。厚生労働省の統計によれば、近年の厚生年金(第1号被保険者)の平均受給額は、毎月およそ14万5千円前後で推移しています。これもまた、物価や賃金の動きに応じた調整が行われており、少子高齢化の影響を受けながらも大幅な増減は避けられているのが現状です。ただし、非正規雇用や短時間勤務者の増加により、将来的には受給額の平均値が低下する可能性も指摘されています。
-
推移から考える将来の生活設計
これまでの年金額の推移から見えてくるのは、「急激な変化はないが、今後も横ばいか微減の傾向が続く可能性が高い」ということです。つまり、老後の生活を年金だけに頼るのはリスクがあるということです。現役世代のうちから、退職金や個人年金、資産運用、iDeCo(個人型確定拠出年金)など、複数の柱を立てておくことが重要になります。また、定年後の再雇用制度や副業によって収入源を確保するなど、柔軟な働き方も検討されるべきでしょう。
-
まとめ
年金の支給額の推移は、単なる数字の変化ではなく、日本社会の構造や経済状況の変化を映し出しています。安定しているように見える国民年金や厚生年金も、人口構成の変化によって将来的に見直しが行われる可能性があります。だからこそ、受け身でいるのではなく、年金制度の仕組みや過去のデータを理解したうえで、自分自身の老後をどう支えていくかを主体的に考えることが求められているのです。