- 2025-1-30
- 医療保険
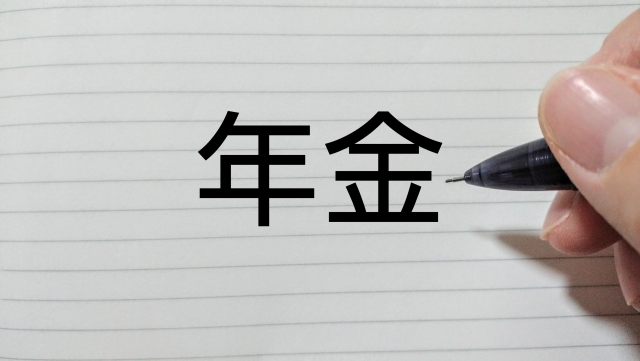
個人事業主として働く人々にとって、老後の生活を支える年金制度は大きな関心事です。しかし、会社員や公務員が加入する「厚生年金」とは異なり、個人事業主が加入するのは「国民年金」が基本となり、その仕組みや負担、将来受け取れる年金額には大きな違いがあります。この記事では、個人事業主の年金事情について詳しく解説し、将来の備えに役立つ情報を提供します。
目次
- 個人事業主が加入する年金制度の概要
- 会社員と個人事業主の年金額の違い
- 年金以外での老後資金準備の方法
- 個人事業主が年金を効率的に活用するためのポイント
- まとめ
-
個人事業主が加入する年金制度の概要
個人事業主は、日本の公的年金制度における「第1号被保険者」として、国民年金に加入する義務があります。国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象となる基礎年金制度です。2025年現在の国民年金保険料は月額16,520円で、加入期間中に支払った保険料を基に、老齢基礎年金として受給します。満額の受給を得るためには、最低40年間の納付が必要です。ただし、納付期間が足りない場合でも、最低10年間の納付があれば一部の年金を受け取ることができます。
国民年金は、加入者全員が同じ保険料を支払い、同じ金額の年金を受け取る「定額制」の仕組みです。これに対し、会社員が加入する厚生年金は、収入に応じて保険料が異なり、受給額もそれに連動して増減する仕組みになっています。個人事業主は厚生年金のように収入による上乗せがないため、老後の年金額は比較的少額になります。
-
会社員と個人事業主の年金額の違い
国民年金のみを受給する個人事業主と、厚生年金を併用する会社員では、老後に受け取れる年金額に大きな差があります。2025年時点で、国民年金の満額受給額は年間約80万円(月額約6万5,000円)とされています。一方、厚生年金を含む会社員の年金額は、平均的な収入の場合で年間150万〜200万円程度になることが一般的です。この差は、個人事業主にとって大きな課題となります。
特に、個人事業主は労働時間が不安定になりがちな上、収入が変動する場合が多いため、国民年金保険料の支払いが難しい時期があるかもしれません。その場合、「免除制度」や「追納制度」を活用することで、将来的な受給資格を維持することができます。
-
年金以外での老後資金準備の方法
個人事業主は、国民年金だけでは老後の生活費を十分にカバーすることが難しいため、年金以外の方法で老後資金を準備する必要があります。そのために活用できるのが、「個人型確定拠出年金(iDeCo)」や「小規模企業共済」などの制度です。
iDeCoは、毎月一定額を積み立てて老後に備える仕組みで、掛金が全額所得控除の対象になるため、節税効果もあります。また、小規模企業共済は、廃業時にまとまった資金を受け取れる制度で、事業主の老後資金として活用できます。これらの制度をうまく利用することで、国民年金の不足を補うことができます。
さらに、資産運用も選択肢の一つです。積立NISAや投資信託などを活用して、老後資金をコツコツ増やす方法は、多くの個人事業主にとって有効です。ただし、リスクを伴うため、慎重な判断が必要です。
-
個人事業主が年金を効率的に活用するためのポイント
個人事業主が年金を効率的に活用するためには、まず、国民年金保険料の支払いを滞らせないことが重要です。また、追納制度を活用して、過去の未納期間を補うことも可能です。さらに、iDeCoや小規模企業共済など、節税効果のある老後資金準備の仕組みを積極的に取り入れることで、年金制度を補完する形で老後の備えを強化できます。
また、事業収入を安定させるための計画も重要です。収入が安定すれば、国民年金保険料の支払いがスムーズになるだけでなく、積立や資産運用に回す余裕も生まれます。老後の資金計画を早い段階から立てることで、より安心できる生活を目指すことができます。
-
まとめ
個人事業主は、国民年金だけに頼ると老後の生活費が十分でない可能性があります。そのため、早い段階からiDeCoや小規模企業共済を利用し、老後資金を計画的に準備することが重要です。また、年金制度の仕組みを正しく理解し、活用することで、老後の不安を軽減することができます。個人事業主としての柔軟性を活かしつつ、計画的な老後の備えを進めていきましょう。














