- 2025-6-28
- 個人年金・年金
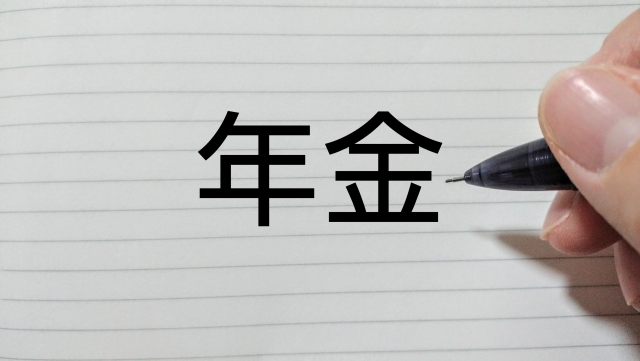
年金は私たちが老後の生活を支えるために積み立てている大切な制度ですが、「一体いつから年金はもらえるのか?」「早くもらうと何が違うのか?」といった受給年齢に関する疑問は、多くの方が抱くものです。年金制度は時代とともに改正され、受給開始の選択肢も増えたため、今の制度を正確に知ることが重要です。本記事では、年金の受給年齢の仕組み、繰上げや繰下げのメリット・デメリット、そして将来設計に役立つ考え方について、わかりやすく解説いたします。
目次
- 年金の基本的な受給年齢とは
- 繰上げ受給の仕組みと注意点
- 繰下げ受給で得られる増額効果
- 年齢選択が将来設計に与える影響
- まとめ
-
年金の基本的な受給年齢とは
現在、日本の公的年金制度では、原則として老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳とされています。国民年金(基礎年金)に加入していた人は、65歳から老齢基礎年金を受給でき、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人は、同じく65歳から老齢厚生年金も受け取ることができます。
かつては60歳から支給されていた時代もありましたが、年金財政の見直しにより、段階的に65歳に引き上げられました。これにより、現代の現役世代は原則65歳を受給の基準として将来設計を立てる必要があります。
-
繰上げ受給の仕組みと注意点
「65歳まで待てない」「生活資金が不安」という方に向けて、60歳から年金を前倒しでもらえる繰上げ受給制度も用意されています。これは最大5年間、つまり60歳から受給開始することができる制度ですが、その場合、1カ月繰上げるごとに0.4%、1年で4.8%、5年で24%支給額が減額されることになります。
この減額は生涯にわたり適用されるため、一度繰上げを選択すると65歳以降に「元の額に戻してほしい」といった変更はできません。また、繰上げ受給中に障害年金や遺族年金と重複して受け取ることができないなど、制度上の制限もあるため慎重な判断が必要です。
-
繰下げ受給で得られる増額効果
一方で、年金の受給開始を66歳以降、最大75歳まで遅らせることができる繰下げ受給制度もあります。繰下げると1カ月ごとに0.7%、1年で8.4%、最大で75歳まで繰下げると42%もの増額が可能となります。
この仕組みは「老後も働き続けて年金に頼らない」「長寿家系なので長く受け取ることが見込まれる」といった人にとっては非常に有利な選択肢となり得ます。年金を受け取る期間が長くなれば、将来的にトータルで得をする可能性があるからです。
ただし、年金の支給を受ける年齢が遅れるため、その間の生活資金は別に準備しておく必要があります。繰下げを選ぶなら、しっかりとした貯蓄や収入の計画が前提になるでしょう。
-
年齢選択が将来設計に与える影響
年金の受給開始年齢をいつにするかという選択は、老後のライフプランに大きく影響します。早く受け取ればその分早く安心が得られますが、長生きすればするほど、受給額が少ないことが生活に響く可能性があります。一方、繰下げて増額を選んだ場合は、老後の後半の生活にゆとりが生まれやすいものの、初期の生活費を自力で工面しなければならないというハードルがあります。
自営業者やフリーランスなど、公的年金以外に収入の見通しが立ちにくい方は、受給年齢をどうするかだけでなく、「そもそも65歳までにどれだけの貯蓄があるのか」「持病や健康状態はどうか」など、総合的な要素から判断する必要があります。
さらに、今後も制度改正の可能性は否定できず、年金の受給開始年齢がさらに引き上げられる可能性もあります。制度が変わる前提で、「今のうちに何を準備できるか」を考えることが、将来の安心につながります。
-
まとめ
年金の受給開始年齢は、現在の制度では65歳が基本ですが、60歳から繰上げて受け取ることも、75歳まで繰下げて増額させることも可能です。それぞれの制度には明確なメリットとデメリットがあり、一人ひとりの生活スタイルや働き方、健康状態、そしてライフプランに応じて、柔軟に選択することが大切です。
年金を「何歳からもらうか」という判断は、老後の生活を大きく左右します。年金制度のしくみを正しく理解し、自分の将来に最適な受給年齢を見極めることで、より安心で安定した老後を築くことができるでしょう。制度の選択肢がある今だからこそ、自らの人生設計と向き合い、賢く備えることが求められています。













