- 2025-3-27
- 医療保険
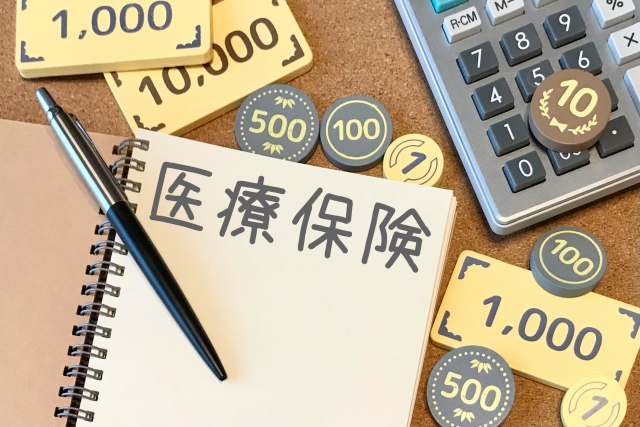
病気やケガをしたときに高額な医療費を支払わなくて済むように、日本には「医療保険」という仕組みがあります。これは、私たちが毎月保険料を支払い、必要なときに医療費の一部を負担することで、誰もが安心して病院にかかれる制度です。本記事では、医療保険の基本的な仕組みや種類、実際の活用方法について詳しく解説します。
目次
- 医療保険とは?
- 医療保険の種類と特徴
- 医療費の自己負担額について
- 高額療養費制度とは?
- まとめ
-
医療保険とは?
医療保険とは、病気やケガをしたときに医療費の一部を負担してくれる制度です。日本ではすべての人が何らかの医療保険に加入しなければならない「国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)」が採用されており、どんな人でも必要な医療を受けられる仕組みになっています。
この制度のおかげで、日本では医療費の自己負担額が抑えられ、経済的な理由で治療を受けられないという事態を防ぐことができます。
-
医療保険の種類と特徴
日本の医療保険は、大きく分けて 「公的医療保険」 と 「民間医療保険」 の2つがあります。
① 公的医療保険(国の制度)
すべての国民が加入する制度で、大きく3つの種類があります。
- 健康保険(会社員や公務員向け)
会社に勤めている人が加入する医療保険で、保険料の半分を会社が負担してくれます。家族も扶養に入れば一緒に保険を利用できます。 - 国民健康保険(自営業や無職の人向け)
自営業の人や、会社に勤めていない人が加入する医療保険です。保険料は加入者が全額負担します。 - 後期高齢者医療制度(75歳以上の人向け)
75歳以上の人が対象の医療保険で、自己負担額が低く設定されています。
② 民間医療保険(個人が加入する保険)
公的医療保険だけではカバーしきれない部分を補うため、民間の医療保険に加入することもできます。例えば、入院時の費用や手術費用を補助する「入院保険」や、がんの治療費を手厚くカバーする「がん保険」などがあります。
-
医療費の自己負担額について
病院で診察を受けたり、薬をもらったりしたときに支払う医療費は、実際にかかった費用の一部だけです。公的医療保険によって、以下のように自己負担額が決まっています。
- 0歳~小学生:自治体によっては医療費が無料または大幅に軽減される。
- 小学生~69歳:医療費の 3割 を自己負担。
- 70歳~74歳:原則 2割 負担。(所得が高い人は3割負担)
- 75歳以上:原則 1割 負担。(所得が高い人は3割負担)
例えば、病院での治療費が1万円かかった場合、69歳以下の人は3,000円だけ支払い、残りの7,000円は医療保険でカバーされるという仕組みです。
-
高額療養費制度とは?
長期間の入院や高額な手術を受けると、医療費の負担が大きくなります。そんなときに助けになるのが 「高額療養費制度」 です。この制度では、一定の金額(自己負担限度額)を超えた医療費が後から払い戻される仕組みになっています。
例えば、収入が平均的な人(標準報酬月額28万円~50万円)の場合、1カ月の自己負担限度額は約 9万円 です。それ以上の医療費がかかった場合、申請すれば超えた分が戻ってきます。
-
まとめ
医療保険は、病気やケガをしたときに経済的な負担を軽減するための大切な制度です。日本ではすべての人が何らかの医療保険に加入しており、健康保険や国民健康保険を通じて医療費の一部がカバーされます。
また、医療費の自己負担割合は年齢によって異なり、高額な医療費がかかる場合には「高額療養費制度」を利用することで負担を抑えることができます。さらに、公的医療保険だけでは不安な人のために、民間の医療保険も選択肢としてあります。
この仕組みを理解することで、万が一のときに備えた適切な選択ができるようになります。健康でいることが一番ですが、万が一に備えて医療保険について知っておくことは、とても大切なことなのです。













